
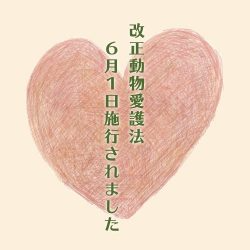
ペットショップにいる子犬や子猫は、小さくてつぶらな瞳でとてもかわいいですよね。 でも、裏では劣悪な環境で育てられていたり、母親や兄弟との早期の別れにより発育に問題を生じてしまうということが多いのが現実です。 そういった状況の改善のため、生後8週(生後56日齢)以下の子犬・子猫の販売を禁止し、よりよい環境で子犬・子猫が産まれ育つようにする「改正動物愛護法」が6月1日に施行されました。
などを解説いたします。 前回の記事はこちら「ご存じですか?動物愛護法」 子犬や子猫が健全に育ち、新しい家族を迎えるために、どんな改正があったのか知ることは大切です。

これまでは、子犬や子猫が7週齢規制(生後50日齢以降ならば販売が可能)とされていました。 かわいくてより小さい方が、売る側にも買う側にもメリットがあるからですね。 ただ、この早すぎる販売時期により、「母親や兄弟との適切な触れ合い時間の欠如」が生じてしまいました。 その結果、
と様々な問題行動を起こす子が増えてしまったのです。 犬や猫の性格は、親から受け継いだものと、子供のときの生活環境によって決まります。 特に「社会化期」という人や他の動物、いろんな音や動きなどあらゆるものに慣れるのに適した時期に、様々な触れ合いや体験をすることは非常に重要です。
 一般的に、社会化期は、
一般的に、社会化期は、
と言われており、この時期の母親や兄弟との触れ合いは、その後の性格形成に大いに関わってきます。
相手を傷つけないじゃれ方を体験したり、母親から様々なルールを教わることで、将来的に人をむやみに噛んだり傷つけたりする困った行動の軽減につながると考えられています。
早期の引き離しによって、うまく意思の表現ができない子になってしまい、結果として飼いきれなくなり手放す飼い主さんが多くなってしまった…ということが問題でした。 また飼育の際の
などの基準がありませんでした。 そのため、劣悪な環境で繁殖、飼育が行われているケースがありました。 しかもそれを取り締まることができませんでした。

上でお伝えした、生後8週(生後56日齢)以下の子犬・子猫の販売を禁止することと同時に、悪質なペットショップや繁殖業者への規制を強化する環境省令も出されました。 具体的には、

などの状態での飼育は禁止し、年に1回以上の獣医師による健康診断を受けさせることや、散歩などを通じて毎日触れ合うようにすることなどがあります。 ケージの広さや高さなどについての数値規制もされ、
といったことも新しく決まりました。
 また、従業員1人でお世話をできる動物の数は限られているため、飼育頭数に上限もできました。 従業員1人当たりの飼育頭数の上限については、新規業者で、
また、従業員1人でお世話をできる動物の数は限られているため、飼育頭数に上限もできました。 従業員1人当たりの飼育頭数の上限については、新規業者で、
既存業者では、段階的な導入がなされ、22年6月からは、
となり、24年の6月からは新規業者と同じ規制が適用されるようになります。

繁殖年齢については、犬猫ともに原則6歳まで(出産回数は犬6回、猫10回まで)とされ、高齢になっても生み続ける…というずさんな飼育はなくなることになります。
今回の改正により細かく数値規制されることで、自治体がペットショップや繁殖業者などに行政処分を出す際の判断基準が明確になりました。
数値規制に関しては準備期間を考慮して、
から導入されるようになっています。 繁殖年齢については新規、既存業者とも22年6月からの導入となり、従業員1人当たりの飼育頭数の上限についての猶予期間は上記の通りです。
環境省は、劣悪な環境におけるペットの飼育について、取り締まりを強化しました。 これによって、子犬や子猫のずさんな管理や生育における問題点が少しでも減少することが期待されています。 ただ、子犬・子猫の社会化期は12~14週齢程度までなので、今後はさらなる引き延ばしを願わずにはいられません。
