

昨今では、ペットの食事の原材料・品質をこだわったり、サプリメントを与えたりと、ペットの健康について考える飼い主様は多くなってきています。
犬や猫の健康状態を維持するうえで、腸内細菌の種類や量のバランスを整えることは極めて重要です。
すなわち、善玉菌の増殖を促進して腸内環境を整える食物繊維や乳酸菌の投与は、ペットにおいても有益と言われています。
この記事では、犬と猫への乳酸菌及び食物繊維の投与の有益性、また期待される効果をお伝えいたします。
様々な研究や開発により、犬や猫への乳酸菌や食物繊維の投与は有益であると考えられています。
どういった点で有用なのかを、乳酸菌・食物繊維それぞれに分けて解説していきます。
乳酸菌は、おなかの調子を整えたり、免疫を強化したりするために、人間では積極的に摂取する栄養素です。
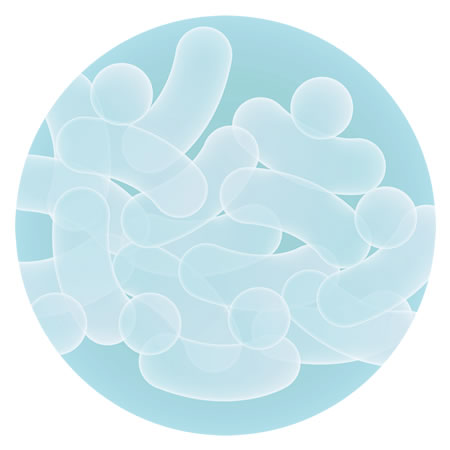
犬や猫においても、おなかを壊したときや日々の健康管理として、ヨーグルトやビオフェルミンなどを与える飼い主様は非常に多いです。
犬に乳酸菌製剤を与えた研究では、抗酸化物質であるビタミンEの腸管での吸収を促進し、生体内における抗酸化力を増加させることが分かっています。
また、乳酸菌などのプロバイオティクスを投与することで、クロストリジウムという腸管内で毒素を産生する菌の発育を抑制し、有益な腸内細菌の有意な上昇を示したといった報告もあります。
犬や猫における乳酸菌投与の効果は他にも、
などと多岐に渡ります。
近年では生活環境の変化から、犬や猫が皮膚炎や消化器症状などのアレルギー症状を示すということも多くあります。
これらは難治性疾患で、通常ステロイドなどの抗炎症薬を用いて治療を行いますが、副作用の面からも、他の治療法や補助療法がないかを模索している獣医師や飼い主様はたくさんいらっしゃいます。
そういった場合に、一般的な内科治療に加えて、乳酸菌製剤が添加されたアレルギー軽減用療法食を用いて治療を行う場合も多くなっています。
最近では乳酸菌が手軽に取れるおやつやサプリメントなども多くあり、犬や猫にとって多くの効果が期待されています。
人の肥満者や糖尿病治療においては、食物の消化吸収を遅延させ、食後高血糖を穏やかにする食事療法が行われています。
食物繊維を豊富にとることもその一端を担いますが、犬や猫においても食物繊維が疾患のコントロールをしたり、日常的に投与するメリットがあります。
そもそも食物繊維は、「粗繊維」としておおよそのペットーフードに配合されている成分であり、原材料としてはトウモロコシや小麦、大麦などがあります。
これらは炭水化物源として、動物のエネルギー活動に重要な役割を果たしています。
最近ではグレインフリー(穀物不使用)のフードが多く出回っていますが、必ずしも穀物を使用していることが悪というわけではありません。
適切な配分で使用している食物繊維はかえって犬や猫に有益となります。
食物繊維には、
の2種類があり、前者は腸の蠕動運動を促進し便通を整える働きが、後者はその粘性により、食物の移送をスムーズにする作用があります。
ペット業界において、それぞれの食物繊維を配合した療法食は多く出回っています。(ロイヤルカナン消化器サポート、ヒルズプリスクリプションダイエットi/d消化ケアなど)
不溶性食物繊維が豊富な食事は、軟便や下痢などの便性状が悪いときに便を固める食事として使用します。(ただし、猫の場合は便秘を助長する可能性があるので投与量に注意します。)
一方で、可溶性繊維が豊富な食事は、便秘傾向にある動物の便を柔らかくし、排出しやすくするために使用します。
また、可溶性繊維については、非ステロイド系抗炎症薬によって引き起こされる腸の潰瘍病変を抑制する効果があるとの研究結果もあります。
犬や猫の腸は、草食動物や人のような雑食動物に比べると非常に短いといった特徴があります。
( 犬の腸:約3.5m、猫の腸:約2m、牛の腸:約50m、人の腸:約8m )
そのため、消化がしやすい肉や魚などの動物性タンパク質を主食とします。
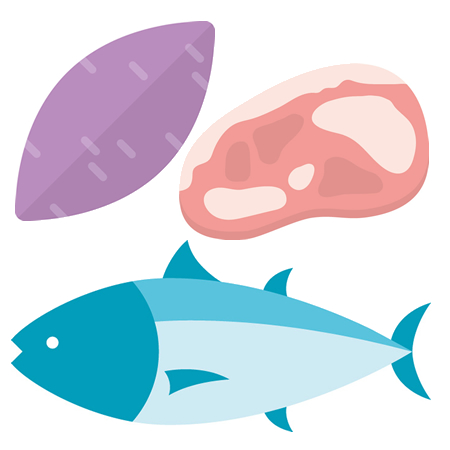
そんな犬や猫においても食物繊維の投与は有用で、
といった健康を保つうえで重要な働きをします。
ただし、犬や猫は食物繊維の分解が苦手なので、食物繊維を大量に与えると消化不良を起こす可能性があります。
そのため、例えば野菜をあげる場合においては、
などと野菜中の繊維分を細かく、柔らかくするなどの工夫をする必要があります。
ペットに乳酸菌や食物繊維を与える事にはたくさんの効果(メリット)がある一方で、デメリットも存在します。
必要以上量を与えると、
と言った症状を示す場合があります。
また、個体によっては合わなくて調子を崩す場合もあります。
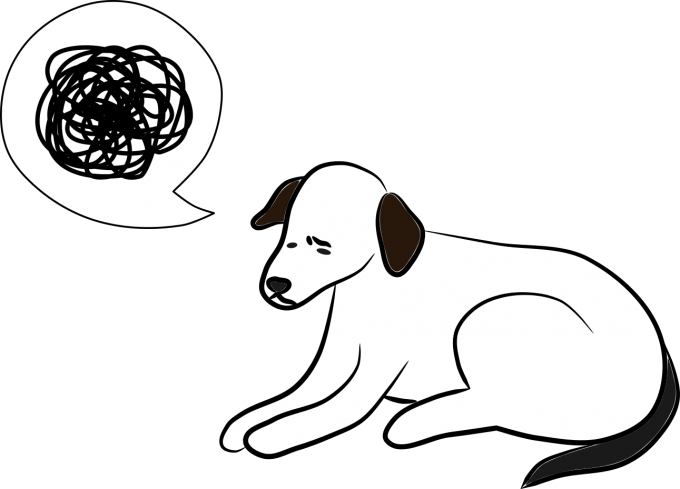
基本的には、通常量で与えている場合には副作用などが出る可能性は低いので、愛犬・愛猫の様子を見ながら投与するようにしましょう。
最近では、犬や猫などのペットにおいても健康志向は高まっております。
中でも馴染みがあり、手軽に始められる乳酸菌や食物繊維の投与は、
などとその効果も多く証明されています。
腸内環境を整えることで、健康状態ひいては健康寿命の延長が期待され、今後ますますそれらを添加した食事やサプリメントの需要が増えてくると考えられます。
今一度、愛犬の健康について考えてみましょう。
