

犬や猫などの動物が健康的に過ごしていくためには、良質なタンパク質の摂取が非常に重要です。
ひとえにタンパク質といっても、肉や魚、大豆などとたくさんの種類があります。
また、それぞれに含まれる栄養価も全く異なるので、どういった効果があるのかを考えながら摂取する必要があります。
この記事では、犬や猫がタンパク質を摂取する必要性と、肉や魚などが持つ栄養面について解説していきます。
愛犬・愛猫の健康的な食事管理について知りたい方は、是非読んでみてください。
犬と猫にとって良質なタンパク質を摂取することは極めて重要です。
栄養素には五大栄養素という、炭水化物・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラルがありますが、そのどれもまんべんなく摂取することが大切です。
中でもタンパク質は、犬や猫などの肉食寄りの動物にとっては大切な栄養素となります。
タンパク質には、
エネルギー源としては、炭水化物や脂質が優先的に使用されますが、エネルギーが不足する場合にはタンパク質も立派なエネルギー源となります。
特に猫は元来肉食動物であることから、炭水化物をうまく利用できないので、タンパク質から糖を作って(糖新生)エネルギー源として利用しています。
そのためタンパク質の要求量が犬に比べて高いという特徴があります。
タンパク質は、血管や筋肉、皮膚や被毛などあらゆる体の構造を作ります。
そのような作用のあるタンパク質を「構造性タンパク質」と呼び、以下のようなものがあります。
| コラーゲン | 骨、軟骨、血管、皮膚、歯など |
|---|---|
| 核タンパク質 | DNA、RNAの材料 |
| 細胞膜 | リン脂質とともに細胞膜を構成 |
| ケラチン | 被毛、爪など |
タンパク質は、酵素や物質の輸送など様々な化学反応に関わる生理活性物質にもなります。
そのような作用のあるタンパク質を「機能性タンパク質」と呼び、以下のようなものがあります。
| 酵素 | アミラーゼやトリプシン、ペプシンなど消化酵素 |
|---|---|
| ホルモン | インスリンやグルカゴン、成長ホルモンなど |
| 生体防御タンパク質 | 抗体や補体など |
| 栄養・酸素運搬タンパク質 | アルブミン、ヘモグロビンなど |
タンパク質には、
動物性タンパク質源としてペットフードに利用される肉類には、牛肉・豚肉・鶏肉・鹿肉などがあります。
 それぞれの肉類には、タンパク質源となることに加え、たくさんの栄養的メリットがあります。
それぞれの肉類には、タンパク質源となることに加え、たくさんの栄養的メリットがあります。
 牛肉は高カロリーなイメージもあるかもしれませんが、豊富な栄養素やそれによる効果が期待でき、良質なタンパク質源として重要です。
牛肉は高カロリーなイメージもあるかもしれませんが、豊富な栄養素やそれによる効果が期待でき、良質なタンパク質源として重要です。
また牛肉にはカルニチン(必須アミノ酸のリジンとメチオニンより作られる)も豊富に含まれており、脂質の代謝に必要不可欠となっています。
他にも牛肉には、
豚肉には、
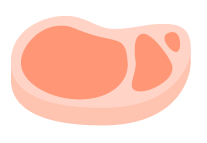 豚肉にはビタミンが豊富というイメージがありますが、まさにその通りで、ビタミンB1においてはなんと牛肉の約8倍近く含まれています。
豚肉にはビタミンが豊富というイメージがありますが、まさにその通りで、ビタミンB1においてはなんと牛肉の約8倍近く含まれています。
 ペットフードには鶏肉(チキン)を使った商品が多くあります。
ペットフードには鶏肉(チキン)を使った商品が多くあります。
鶏肉を使用したフードは、低脂質・低カロリーで良質なタンパク質が摂取できることが最大のメリットで、ダイエット食としてもよく利用されるタンパク質源です。
また、ビタミンA(成長促進作用、抗眼乾燥症、抗菌力増強作用など)やビタミンB群も豊富に含まれ、部位により様々な栄養を摂れるので幅広く利用されています。
 最近では野生の鹿による農地や民家への被害が多く、鹿を捕獲する機会が増えてきています。
最近では野生の鹿による農地や民家への被害が多く、鹿を捕獲する機会が増えてきています。
捕獲した鹿肉を無駄なく使用するために、ジビエ料理として提供されたり、ペットフードなどによく利用されるようになりました。
牛肉や豚肉と比べるとタンパク質含量が高く、脂質が少ないことが特徴です。また、
魚由来のタンパク質は、肉類に比べるとカロリーが低くヘルシーであり、また肉アレルギーがある場合などに利用されます。
 主に使用される魚介類として、
主に使用される魚介類として、
 赤身魚とは、ミオグロビンという血色素タンパクが多い魚のことを言い、身が赤く見えることが特徴です。
赤身魚とは、ミオグロビンという血色素タンパクが多い魚のことを言い、身が赤く見えることが特徴です。
赤身魚は白身魚に比べると栄養価が高く、
 白身魚は、赤身魚に比べると血色素タンパク質が少ない魚のことを言い、身が白く見えることが特徴です。低カロリーで良質なタンパク質を摂取できることから、筋力維持やダイエット食として主に利用されます。白身魚の一つであるサーモンにおいては、アスタキサンチンという天然色素が含まれており、抗酸化作用が強いことから健康面で着目されています。
白身魚は、赤身魚に比べると血色素タンパク質が少ない魚のことを言い、身が白く見えることが特徴です。低カロリーで良質なタンパク質を摂取できることから、筋力維持やダイエット食として主に利用されます。白身魚の一つであるサーモンにおいては、アスタキサンチンという天然色素が含まれており、抗酸化作用が強いことから健康面で着目されています。
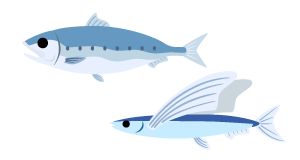 青魚とは、赤身魚のうち背中部分が青く見える魚のことです。背中が青く見える理由は、不飽和脂肪酸のDHA(ドコサヘキサエン)やEPA(エイコサペンタ塩酸)を多く含むからです。DHAはコレステロール値の上昇を抑えたり、肝臓での中性脂肪合成を低下させる働きがあり、EPAは血栓予防や血管の収縮を抑える効果があります。赤身魚もこのDHAやEPAを含んでいますが、青魚はそれよりはるかに多く含有しており、健康維持のために昔から着目されています。また、青魚より採取される魚油には、これら栄養素が濃縮されており、効率よく摂取することが可能です。
青魚とは、赤身魚のうち背中部分が青く見える魚のことです。背中が青く見える理由は、不飽和脂肪酸のDHA(ドコサヘキサエン)やEPA(エイコサペンタ塩酸)を多く含むからです。DHAはコレステロール値の上昇を抑えたり、肝臓での中性脂肪合成を低下させる働きがあり、EPAは血栓予防や血管の収縮を抑える効果があります。赤身魚もこのDHAやEPAを含んでいますが、青魚はそれよりはるかに多く含有しており、健康維持のために昔から着目されています。また、青魚より採取される魚油には、これら栄養素が濃縮されており、効率よく摂取することが可能です。
DHAやEPAは体内で合成することができないので、食品として積極的に取り入れる必要があります。
肉食寄りの動物である犬や猫にとって、タンパク質は、
